行政書士が貴社の許認可をサポート
建設業を中心に、許認可関連の手続き、管理をサポートいたします。複数の許認可を持っている企業様の許認可管理も承ります。
Support

サポート内容
-
Support01
建設業許可、経審、
入札参加(工事)サポート -
Support02
入札参加資格の取得・管理サポート(100〜1,000申請の一括管理)
-
Support03
外国人の就労ビザ申請
-
Support04
許認可一括管理サポート
-
Support05
宅建業者向けサポート
-
Support06
産業廃棄物処理業者向けサポート
サポート料金
一般的な報酬額は以下の通りです。
詳細についてはお問合せ後にお見積りを提示させていただきます。お気軽にご相談ください。
※表示価格はすべて税別です。
|
建設業向けサポート 建設業許可の取得、更新、年次報告、各種手続き、経営事項審査(経審)、入札参加資格 |
||
|---|---|---|
| 建設業許可 | 新規 | ¥150,000~¥250,000 ※大臣許可は別途お見積りさせていだきます。 |
| 建設業許可 | 更新 | ¥100,000~ |
| 年次報告 | ¥45,000~ | |
| 各種変更手続き | ¥20,000~ | |
| 経営事項審査 | ¥120,000~ | |
| 入札参加資格 | ¥30,000~/1自治体 ※複数自治体でお値引きを適用させていただきます。 | |
-
入札参加資格の取得・管理サポート
入札参加資格の取得
-
¥30,000~/1自治体
※複数自治体でお値引きを適用させていただきます。
-
許認可一括管理サポート
複数の許認可をお持ちの事業者様向け
期日情報を一括で管理し、許認可に関する各種手続きをサポート -
個別見積り
|
外国人の就労ビザ申請 技術人文国際業務、特定技能ビザ取得サポート、経営管理ビザ、日本法人設立サポート |
|
|---|---|
| 在留資格認定 | ¥100,000~¥250,000 |
| 在留資格更新 | ¥150,000~ |
| ビザ種類変更 | ¥100,000~¥150,000 |
-
宅地建物取引業免許
-
¥150,000~
-
産業廃棄物収集運搬業許可
-
¥120,000~/1自治体
※複数自治体でお値引きを適用させていただきます。
-
中間処理施設設置許可
-
個別見積り
ご相談の流れ

お問い合わせ
お電話またはフォームよりお問い合わせください。

お打合せ
ご状況、ご希望の詳細をヒアリングさせていただきます。
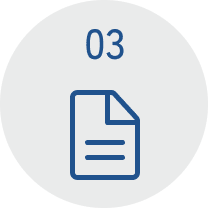
ご提案の共有
ヒアリング内容を基に、ご提案させていただきます。
ご提案時に見積りも作成いたしますので、併せてご確認いただきます。

ご契約・業務の遂行
提案及び見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。必要な準備が整い次第、対象業務を実施し、ご報告・ご説明をさせていただきます。
許認可部門担当紹介

行政書士
千葉 直美Naomi Chiba
許認可部門リーダー
行政書士セクションにて、建設業等の各種許認可業務、入札業務をメインに企業のサポートをしております。
これからもお客様の企業経営のますますの発展のため、お客様と行政の架け橋となり、煩雑な行政手続きを迅速に対応してまいります。ぜひ一度ご相談くださいませ。
- 2016年11月
- 入社
- 2018年10月
- 行政書士法人の社員に就任
現在に至る











